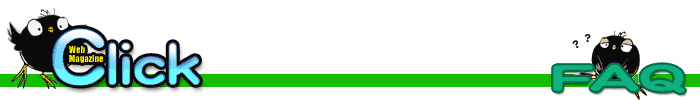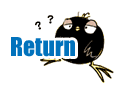最近、新聞、テレビのニュース等で報道されているように、インターネットを通じた破壊者(クラッカー)よるコンピュータへの侵入や、ソフトウェアに潜んだコンピュータウィルスによるシステム破壊など、コンピュータを使用した様々な事件が起こっています。
今回そのセキュリティについて、プロバイダーやシステム管理者がやるべきこともありますが、まずはその前に身近なところで、自分のセキュリティを守るために、知っておいたほうがいいこと、自分でできる対策などを紹介します。
個人利用者のセキュリティ対策
1. 個人情報の取り扱い
- 自分の個人情報を過度に知らせない。
- 他の人の個人情報に十分配慮する。
2. ウィルス ・ ウィルスチェックリストを導入し常に更新する。
- 自万が一の被害に備えるためデータのバックアップを行う。
- 添付ファイルはむやみに開かない。
3. パスワードの再チェク
- 自分の名前、電話番号、誕生日等をパスワードに使わない。
- パスワードは定期的に変更する。
- パスワードはどこも同じにしない。
4.チェーンメールについて
1.個人情報の取り扱いについて
インターネットは世界中とつながって、とても便利なものですが、これを逆に考えると、世界中の誰もが、あなたへのアクセスが可能だといえます。知らない人や企業から送られる製品宣伝、ネズミ講まがいの怪しい商売の案内、下品な電子メールの類が届くトラブルも増えてきています。では、このような好ましくない人からアクセスされないように自分のプライバシー情報を過度に知らせない上での注意点は以下のものが挙げられます。
- メーリングリストで不用意に情報(電話番号等)を発信しない。
- プレゼントやアンケートで誘う個人情報収集ページに書き込む前に考える。
- 訪問者ボタンを押す前に考える。
- ホームページやメールの署名(シグネーチャ)に個人情報を入れない。
- ソフトウェアの設定での個人情報入力は最小限にする。
2.ウイルス
コンピュータウィルスは、マシンに感染し増殖する能力をもつ悪質なソフトウェアをいいます。ウイルスの中にはコンピュータを動かなくしたり、システムを立ち上がらなくしたり、ファイルを削除・破壊したり、画面にメッセージをはき出す自己主張の強い種類があり、往々にしてコンピュータに被害をもたらします。ウイルスに感染しないための注意点は以下のようなものです。
- 最新のワクチンソフトを活用しましょう。
- 万一のウイルス被害に備えるためデータのバックアップを行いましょう。
- ウイルスの兆候を見逃さず、ウイルス感染の可能性が考えられる場合ウイルス検査を行いましょう。
- メールの添付ファイルはウイルス検査後開きましょう。
- ウイルス感染の可能性のあるファイルを扱う時は、マクロ機能の自動実行は行わないようにしましょう。
- 外部から持ち込まれたFD及びダウンロードしたファイルはウイルス検査後使用しましょう。
参照 F.A.Q ウィルス編
3.パスワードの再チェック
パスワードを設定し、管理することはセキュリティの基本です。パスワードを管理する上での注意点をいくつか挙げます。
- 自分の名前、電話番号、誕生日等をパスワードに使わない。
- パスワードは定期的に変更する。
- パスワードはどこも同じにしない。
パスワードを人が予想できる文字列にすると解読される確率が高くなり、非常に危険です。また、パスワードは長い間同じものを使っていると解読される確率が高くなるので定期的に変更することも大切です。
また、全て同じパスワードをつけると、どこか一カ所のパスワードが漏れたとき、その他のところでも利用される可能性がありますので注意が必要です。
4.チェーンメール
チェーンメール(chain mail)は、不特定多数の人々の間を増殖しながら転送されていくことを目的としています。
チェーンメールが増えると、飛び交うメール量が一気に増え、ネットワークやメールサーバに負担がかかります。電子メールは郵便に比べ転送が容易なことから、爆発的に広がる危険性を持っています。
内容は、ねずみ講の勧誘やデマが多く、ほとんどはいたずら目的のものです。しかし最近は、有名企業からのウィルス情報や人気テレビ番組の企画と記載される等、巧妙になっているため、いつの間にかチェーンメールの増殖に加担してしまったというケースが増えてきています。
メールを転送する際には、情報が本当のものかどうか見極める必要があります。
|