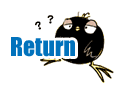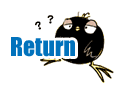ワクチンソフト
ウイルスを発見・駆除するソフト。コンピュータがコンピュータウイルスに感染していないかどうかをチェックし、感染しているファイルからウイルスを取り去るソフト。ウイルスに侵されたファイルは、そのウイルスに対応できるワクチンでウイルスは除去できる。しかし、新種のウイルスには対処が難しい。
CHI
チェルノブイリという物騒な名前でも知られているW95/CHIは、マシンをブートできなくすることもあるという、凶悪性の高いウイルスである。1998年に発見され、99年にアジアを中心に大きな被害をもたらした。Windowsのポータブル実行ファイルの形式を取るが、WindowsNT/2000には感染せず、Windows95/98だけに感染する。
Happy99
W32/Sha.Aは99年に急増したメールを使って広がるウイルスの一つである。ディスクを壊すといった実害は少ないものの、IPAに1999年に届けられたウイルスの27%を占め、Excelマクロ・ウイルスのLarouxと並んで、国内では一番多く見られたウイルスの一つである。
Melissa
W97M/Melissaは、Word97のマクロを使ったウイルスである。ただ、WordのマクロであることよりもOutlookを使って自信をメールで送りつけることで有名になりました。数多くの企業メールシステムをパンクさせ、駆除が進までメールが麻痺しました。
ExploreZip
W32/ExploreZipは、凶悪性の高いウイルスである。ファイルに感染するのではなく、システムに居座り、ネットワークを介して広がっていくという点で、厳密にはウイルスではなく、ワームと分類される。
BubbleBoy
VBS/BubbleBoyは2000年3月までのところ、メールを開いただけで感染する唯一のウイルスであった。特に実害はなく、感染報告もほとんどない。メールを開いただけで感染するウイルスが可能であることを実証するためだけに作られた実験的ウイルスであると考えられている。
BubbleBoyはOutlook/Outlook ExpressのHTMLメールの機能を使う。HTML内にVBスクリプトを書き、それがウイルスとして動作する。これを防ぐには設定で、セキュリティーゾーンを「制限付き」に変える必要がある。
侵入
ウイルスがコンピュータ内において実行できる状態になること。
寄生
ウイルスが他のプログラムに侵入してそのプログラムを利用しながら動作すること。
感染
ウイルスが他のプログラムに侵入して仲間を増やすこと。
増殖・繁殖
ウイルスが自己を複製して仲間を増やしていく様子(コンピュータ内部・コンピュータから他のコンピュータへ)。
伝染
現在ウイルスが侵入しているコンピュータから他のコンピュータに自己複製して再侵入し、同様な状態になること。
潜伏
ウイルスがコンピュータシステム内にあってまだ発病してない状態。
トリガー
ウイルスの不正命令(破壊命令など)が実行される論理的なきっかけ。
発病
トリガーにより不正行為が実行されて、正常なコンピュータ機能を阻害しはじめること。
ハングアップ
コンピュータ利用中に動作が異常になり、キーボードやマウスからの入力操作を全く受け付けない状態。
情報処理振興事業協会(IPA)
情報処理の振興を目的とした唯一の公的機関。「情報処理の促進に関する法律」に基づいて1970年に設立された特別認可法人で、国や政府関係機関からの出資金と助成金などで運営されている。
|